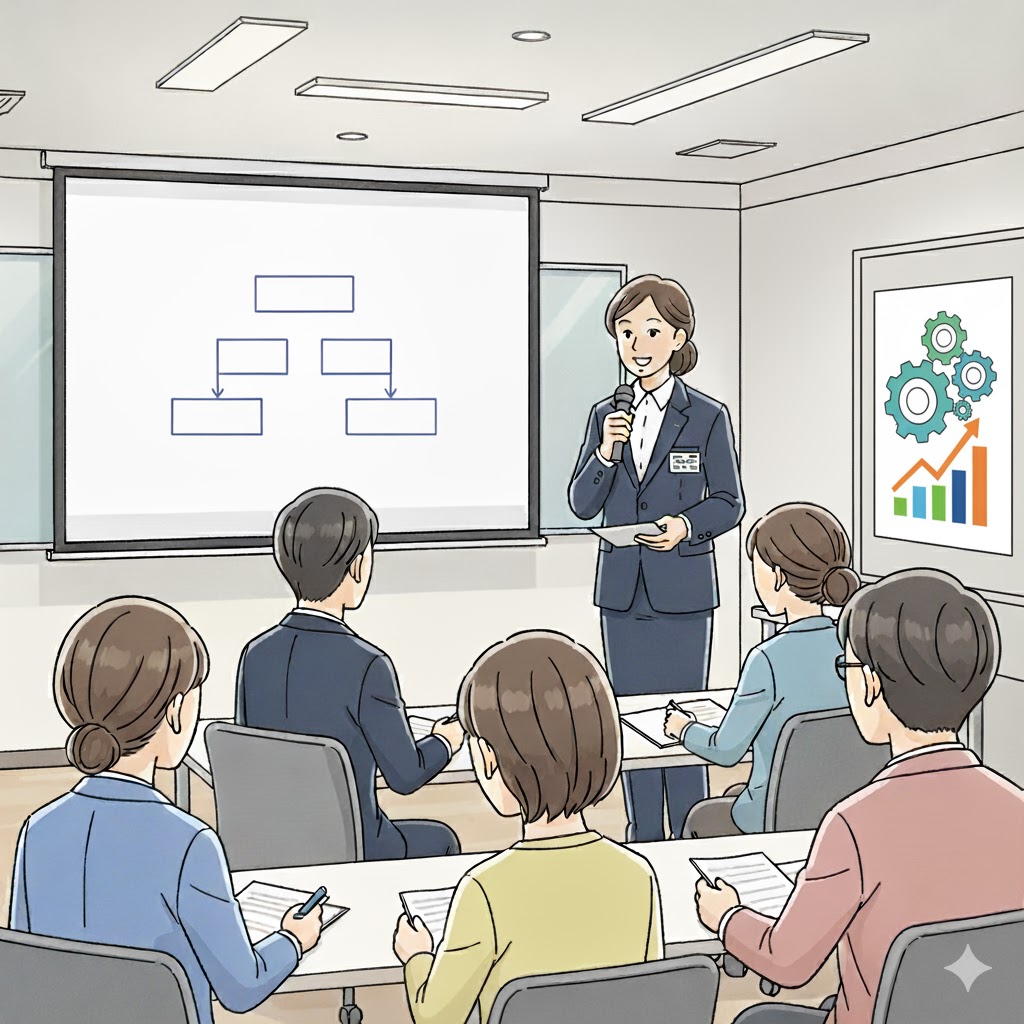税理士は税務署、市役所区役所などと連携し、税の相談会や説明会で活動しています。私も年に何度かこのような活動に携わっています。
その一つに、「法人の決算説明会」があります。
今回は、私がそこでどのようなことを説明し、どのようなことを最も伝えたいと考えているかをご紹介します。
決算説明会ではどのようなことを話すのか
私が所属する地域では、税理士は法人税申告についての説明を担当します。
その説明会では、会社の決算・申告の仕方を書いた冊子を使います。
決算で何をしなければならないか、申告では何を書かなくてはいけないかなどを説明します。
ただ時間が限られているので(私が担当する時間は50分)、当然すべてを丁寧に説明することはできません。
また50分ですべてを理解することも難しいでしょう。
その50分で私がまず伝えることは、決算申告業務の全体の流れと期限です。
会社の業務によって決算申告事務の内容は異なります。
しかし、すべての会社で共通しているのは「申告には期限があること」です。
その期限までになにをするのか把握し、その内容を会社に持ち帰っていただきたいと考えています。
会社の決算申告業務の流れ
①日々作成している帳簿をもとに決算調整をおこなう
②決算書類等(B/SやP/Lなど)を作成
③株主総会で承認を得る
④申告調整をおこなう
⑤法人税の申告書を作成する
⑥提出、納税をおこなう
法人税の申告書提出期限は、原則として決算締日の翌日から2か月以内です。
2か月という期間は、事務処理の量と内容を考えると、かなりタイトです。
ですからまずは提出期限をゴールと設定し、「いつまでに、何をやらなくてはいけないか」の予定をたてることが必要となります。
予定をたてるために、決算申告業務の大まかな内容をイメージしておくことが大切です。
知っておくべき法人税の考え方
決算申告事務をスムーズに理解するために、知っておくべきことがあります。
法人税は、所得税と同じく原則として利益に課税されます。
しかし法人税を計算するときは、税金を計算するために会社の利益を調整するのが特徴です。
会社の決算書類等は、以下の2つの役割があります。
①経営の診断書:会計の流れを記録から把握し、経営判断の材料となる
②対外的な報告資料:銀行や株主など、社外の利害関係者への報告資料
税金では「公平であること」を重視します。このため法人税の計算では、株主総会で承認された対外的な報告資料である決算書類等に、税法独自の考え方で調整を加えて、「課税所得」を算出します。
つまり、「会社利益」と「課税所得」は違うということを理解するのが、第一歩です。
この流れを意識するだけで、いま何の処理をしているのかがクリアになり、処理がスムーズになります。
具体的に実務処理ポイントを説明する
説明会に参加する方の多くは、税理士に頼まず自社で経理や申告をする小規模な会社です。
そのため説明はそうした会社が実務で直面すると予想されるものにしぼっています。
説明する項目は、決算で数字を合わせるべき勘定科目、売上の計上時期、減価償却の方法などですが、ここでは税法の難しい規定の説明は最小限にとどめます。
そして実務でのポイントや処理にあたっての注意事項を中心に説明していきます。
今回は、あくまでも私個人が、どのようなことを考えて説明をしているかを書いています。
各税理士により、説明の方法や優先すべきと考えていることは違いますが、なるべく納税者にわかりやすいように説明したいと考えていることでしょう。
税理士は、今回ご紹介したような税の相談会や説明会など、公的な活動も行っています。 そして、お客様の申告書作成だけでなく、こうした社会貢献活動を通じて、地域の皆様の税務をサポートしています。
決算や申告の準備で不安に思ったり、相談したいと思った場合は、税理士に声をかけてみてください。
こうした不安をうかがい、会社やその人に合ったやり方を一緒に考えるのが、税理士の役割でもあります。